 ここにも、みすゞさんのすれ違い人生があった。それは文豪、志賀直哉である。私の愛読書に、司馬遼太郎の『街道をゆく』のシリーズがある。その二十四巻の「奈良」の一行に私の目はくぎづけになった。
ここにも、みすゞさんのすれ違い人生があった。それは文豪、志賀直哉である。私の愛読書に、司馬遼太郎の『街道をゆく』のシリーズがある。その二十四巻の「奈良」の一行に私の目はくぎづけになった。
─
明治四十一年(1908)、政府は勅令をもって、奈良に高等師範学校を設けた。政治も文化も、中心が関西から東京へと移っていくとき、奈良に女子師範ということは、奈良の文化面での没落をある意味で救った。─
こんな内容のことが書かれていた。金子みすゞは大津高女を卒業するとき、その優秀な成績から、奈良女子師範への進学を強く勧められている。しかし彼女は、教員室の雰囲気や女教師という職になじめず、これを固く辞退したという話は有名である。
さて、話は志賀直哉である。前記『街道をゆく』につぎの記述がある。─
志賀直哉の奈良移住は大きかった。年譜を見ると、大正十四年(1925)、四十三歳のときに移住し、昭和十三年(1938)五十六歳で東京に引きあげている。この間、奈良の志賀家に来遊したひとの数はかぞえきれない
─。先生が奈良に移られてから、龍井孝作さん、舟木重雄さんも移られた。武者小路実篤先生も一年ほど奈良に住まれた。東京と違って、歩いて行ける市内のことだからお互いの往来は容易だった。─
つまり、志賀直哉中心に、大いなる文学サロンが形成され、いまもなおその影響が残っているというのだ。あの関東大震災は、首都東京を壊滅状態にし、日本のよき伝統風俗まで滅していった。志賀の心は傷み、国のまほろば奈良への回帰となったのだろうか。「イフ(もしも)ということが許されるなら、みすゞさんが奈良師範に入っていたら。志賀直哉と会っていたら・・・。」私の胸中に楽しい想像がふくらむ。みすゞさんと直哉と実篤の楽しい静かな語らいの時間。いったい何が語られていくのか。これは私の楽しい白昼夢。
みすゞさんのファンには叱られるだろう。もし前述のようなことになったら、あのみすずさんのつくりあげた「みすゞコスモス」はなくなるのではないか。みすゞさんはみすゞさんの宇宙を自らつくり完結したものだから、もしそれがなくなれば人類の一大損失だと。それはそうとして「イフということが許されるなら・・・」これも私の楽しい白昼夢。
注)
記事内容は変わりませんが、長文故に段落位置の変更、および花の写真の挿入はホームページ用に、手を入れさせて頂きました。実文は縦書きで筆者名は次項のサインが使われていました。また本文のあとに下記、<編集室>の追悼文が載っています。
|
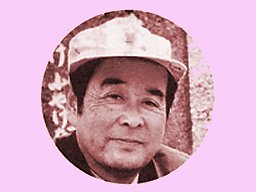

 山口県の隣の、島根県にも三隅という町があります。その三隅町に地元出身の日本画家、石本正(いしもとしょう、1920-
)氏の作品が見られる、イタリア教会風の町立美術館(2001.04開館)があります。石正(せきしょう)美術館と言いますが、地域の方とのふれあい、県内近隣の美術館と交流を図りながら、独自のスタンスを持って運営されています。
山口県の隣の、島根県にも三隅という町があります。その三隅町に地元出身の日本画家、石本正(いしもとしょう、1920-
)氏の作品が見られる、イタリア教会風の町立美術館(2001.04開館)があります。石正(せきしょう)美術館と言いますが、地域の方とのふれあい、県内近隣の美術館と交流を図りながら、独自のスタンスを持って運営されています。
 林芙美子とみすゞ
林芙美子とみすゞ ここにも、みすゞさんのすれ違い人生があった。それは文豪、志賀直哉である。私の愛読書に、司馬遼太郎の『街道をゆく』のシリーズがある。その二十四巻の「奈良」の一行に私の目はくぎづけになった。
ここにも、みすゞさんのすれ違い人生があった。それは文豪、志賀直哉である。私の愛読書に、司馬遼太郎の『街道をゆく』のシリーズがある。その二十四巻の「奈良」の一行に私の目はくぎづけになった。 <編集室>
<編集室>